獨協医科大学 医学部 麻酔科学講座 主任教授 山口 重樹 先生
対談担当者:鈴木 勉(一般社団法人 医薬品適正使用・乱用防止推進会議代表理事)
山口重樹先生のご略歴
 1992年 獨協医科大学医学部卒業
1992年 獨協医科大学医学部卒業
1998年 獨協医科大学大学院卒業
2000年 米国The Johns Hopkins大学留学
2006年 獨協医科大学病院腫瘍センター緩和ケア部門長
2007年 獨協医科大学麻酔科学講座准教授
2012年~獨協医科大学麻酔科学講座主任教授
2013年~順天堂大学大学院医学研究科環境医学研究所客員教授(兼任)
2014年~名古屋市立大学医学部麻酔・危機管理医学分野非常勤講師(兼任)
~Question1~
鈴木)
WHO 方式がん疼痛治療法が日本に導入されてから30年が経過しましたが、がん疼痛治療は十分に行われているのでしょうか。特に、がん治療医の先生方は如何でしょうか?
山口)
私の印象ですとWHO式がん疼痛治療法は、終始徹底して使われていると思います。辛い痛みを訴えているのに医療用麻薬が投与されない患者はかなり減ったはずだと思います。ただ、十分な量の医療用麻薬が処方されているかどうかは疑問が残ります。薬を出したら終わりというのが今の問題点ではないかという風に思います。
WHO方式がん疼痛治療法に従って、医療用麻薬の投与が開始されていると思いますが、その後のアセスメント不足により十分な量が投与されていない場合が多いと思います。
多分、そのことが日本の医療用麻薬の消費量の低迷にも反映されているのではないかと思います。ですから30年が経ってWHO方式がん疼痛治療法は、日本においても浸透はしているが、まだまだ検討の余地があると思います。
鈴木)
患者が痛いと言わないケース、我慢してしまうケースがあると思うのですが。その辺はいかがでしょう?
山口)
もちろんそれはあると思います。
例えば、初めて辛い痛みを感じた時に、多くの患者が病気はそんなに悪くないという風に自分に言い聞かせてしまうことがよくあります。
ですから「一晩寝ればよくなるだろう」というような気持ちで我慢している患者が多いのではないかと思います。
しかし数日続く痛みに我慢できなくなってくる、家族が見かねて連絡してくる、また入院患者などは病棟スタッフが主治医に話をしてくるというような場合も少なくなく、見るに見かねて医療用麻薬が投与されることもあります。ですが、辛い痛みを訴えている患者がずっとほっておかれるとう状況は滅多にないと思います。
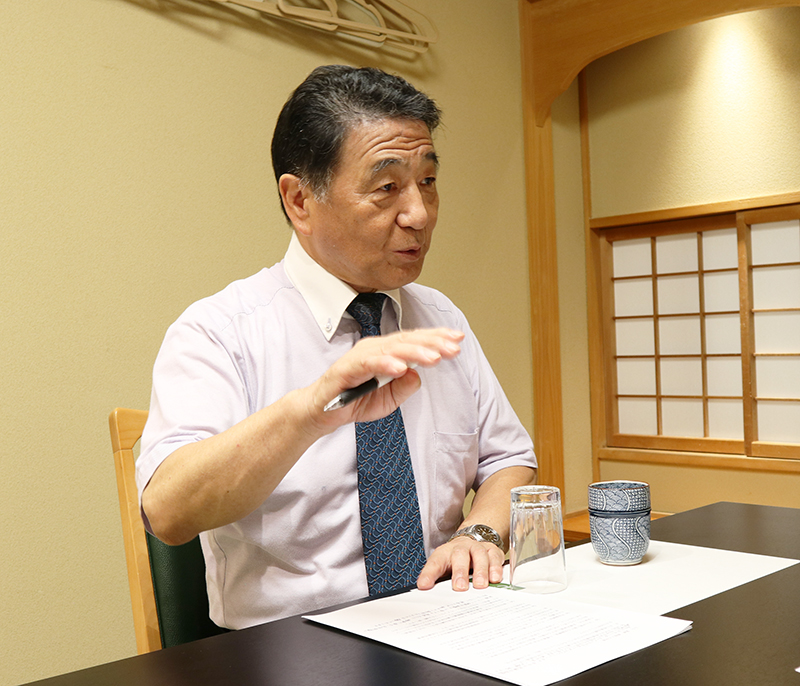 ~Question2~
~Question2~
鈴木)
「がん対策に関する世論調査」の概要が平成29年1月内閣府政府広報室より発表され、医療用麻薬に対する印象は「最後の手段だと思う」や「だんだん効かなくなると思う」が約30%、「一旦使用し始めたらやめられなくなると思う」が約15%でした。この結果を先生はどのようにお考えでしょうか?
山口)
決して不思議ではない結果かと思います。
どうしても「がん」と言う言葉が「死」をイメージする言葉だと思いますので、やはり「薬」の前に「死」をイメージしてしまうのは当然のことだと思います。
加えて、医療用麻薬の話題が出てくるので、医療用麻薬は最後の手段であると言うような考えに繋がってしまうのではないでしょうか。
そのことはどうしても払しょくできないことかと思います
抗がん剤治療が効かなくなってから始める薬だと言うイメージもあるのではないかとも思います。
だんだん医療用麻薬が効かなくなると言うのは、それまでの経験の中で様々な薬(市販薬等を含めて)を使った経験の中から「効かなくなっていった」という経験が影響しているように思います。
量を増やしたり、上手く調整すればまた効くという重要な教育がなされていないと思います。
大抵の鎮痛薬、例えばNSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)であるとか、アセトアミノフェンは市販薬で買えますし、1日の用量が決まっているので、痛みの強さに応じて増やしたり、減らしたりという経験はないと思います。そうすると効かなくなってしまうのではないかと言う思いになってしまうことは不思議ではありません。
このように考えてしまうのは仕方がない事だと思います。
ですので、ここの部分は私たち医療者がきちんと患者の誤解を解いていく必要があるのではないでしょうか。
先ほども話しましたように一旦医療用麻薬による治療を始めたら止められなくなるという風に考えてしまうことも多いでしょう。
どうしても「がん」と言う病気ですので、亡くなる最後まで医療用麻薬を使っていたと言う印象があるのではないかと思います。
ですからそのような数字が出てくるのもおかしなことでは無いと思います。
でも「やめた」「やめることが出来る」と言うような事もきちんと説明しなくてはいけないと思います。
慢性疼痛での医療用麻薬の使用においては、私は多くの医療者に「やめる」のが当たり前だと言う教育をしています。例えが悪いかもしれませんが、お菓子のCMにあったような「やめられない、とまらない…」ではないと、きちっと説明していく必要があると信じています。
がんの治療が奏効すれば、痛みは軽減され、医療用麻薬の必要性はなくなり、やめられるということが強調されるべきです。
鈴木)
今の問題に関連してがんサバイバーが増えていますが、ここで言った内容がかなり変わってくると思います。
今後がんサバイバーがかなり増えてきた時に、どのように教育していくのかが大切だと思うのですけれどもいかがでしょうか?
山口)
個々のがんサバイバー、例えば「根治できたが、痛みは残っている患者」「根治でき、痛みは残っていないが漫然と鎮痛薬を投与される(鎮痛薬をやめられるはずの)患者」あるいは「根治できていないが、制がんされている(がんが落ち着いている)患者」、あるいは「がんの進行が非常にゆっくりな患者」、「今後がんが進行、転移の可能性が予想される患者」と言うようにいくつかの患者の状況に合わせた痛みの治療を考えていく必要があります。
最近、国際疾病分類が改訂され(ICD11)、「がん性慢性疼痛」と言う言葉が使われるようになっています。
がん患者が自覚する痛みが長期化、複雑化していることが反映されてきているのではないでしょうか。
要するに、WHOが初めて独自のがん疼痛治療法を発表した1986年では、がん治療もごく限られていて、多くの進行がん患者の余命は数週間、数か月と限られていたのに対して、近年のがん治療の躍進を考慮して、長期がんサバイバーという言葉が使用されるようになったことと一緒で、がんの痛みも「がん性慢性疼痛」と言う言葉で理解しようという試みだと思われます。
米国臨床腫瘍学会が長期がんサバイバーの慢性疼痛に対する治療方針を発表するに至っています。
 ~Question3~
~Question3~
鈴木)
内閣府の同世論調査で、がんのために痛みが出て、医師から医療用麻薬の使用を提案された場合、使用したいと思いますか?との質問に対して「どちらかと言えば使いたくない」と「使いたくない」との回答が、40代(31.5%)、30代(38.0%)、20代(39.6%)と増加を示しています。このような状況に対する対策やお考えをお話しいただければと思います。
山口)
よく鈴木先生がおっしゃられているような「ダメ。ゼッタイ。」と言うような教育を受けた世代というのは一つ事実だと思います。
やはりこの世代では、医療用麻薬と覚せい剤、その他の危険ドラックを一緒の様に考えてしまっているのではないでしょうか。
そのためイメージとして「使いたくない」という印象になっているのかなとは思います。
もう一つは理由としては、若い世代では身近に「がん」を感じていない、感じられないのではないでしょうか。そして、「がん」で苦しむ人を目の当たりにした経験も少ないのではないでしょうか。
ですから、どれだけがんによる痛みが「痛い」か、というイメージができず、このような結果になっているのではないでしょうか。
このような背景としては、やはり核家族化が進んでいて、家族が遠くに住んでいたり、身近に「がん」で療養する人を見る経験が不十分だという事の結果であるとも考えます。
鈴木)
このまま推移していけば抵抗を持つ人が増えていくし、がん患者も増えますから、何らかの対策を講じていかなければならないと思っています。
山口)
自分は医学部や看護学部で教えていますが、医学生や看護学生の様な将来の医療を担う学生に対して、「医療用麻薬の誤解を解く」と言った教育を積極的に行っています。麻薬と覚せい剤の薬理学的な違い、非合法麻薬と医療用麻薬の違いを教え、医療用麻薬であれば適切に使えば患者のQOLを上げると言うような事を教えています。
そういった教育を今後は、医療系の学生のみならず、多くの若者、もちろん、小学校、中学校から段階的に繰り返して教えていく必要があると思っています。
鈴木)
出来れば、がん教育が小学生からスタートしていますので、その中にどんどん組み入れて頂ければと私は思っています。
是非、教育に医療用麻薬の必要性と適正使用の推進と言うことを入れていただきたいと思っています。
山口)
私はいつも思っているのですが、今の小学生や中学生の親世代は40代・30代・20代です。ですから子供だけではなくて親子一緒に教育するのが一番早いのではないかと考えています。
積極的に教育委員会等に働きかけて、随分前からやっている「命の教育」等の中に「がんの教育」を入れてはどうかと思います。
がんは2人に1人がなる時代で避けられない病気ですし、予防する方法もあれば、治療する方法もある、治療だけではなくてがんと一緒に生活していける時代が来る、がん療養中に自覚する様々な症状を和らげる事の重要性、そして緩和できることを教えていく必要があると思います。
その中の一つが医療用麻薬であると言うような流れで教育していくことが重要ではないでしょうか。
鈴木)
当法人でも教育資材を色々作って皆様に使って頂き、医療用麻薬に対する誤解や偏見をなくし、適正使用と乱用防止の推進を行っておりますので、ご協力をお願いいたします。
山口)
いろいろあると思うんですね。
「理解できる」「理解できない」何れにしても、一度、このような教育を子供たちにも行うべきだと思います。
例えばそれが幼稚園でも、小学校でも良いです。
もしかしたら忘れてしまうかもしれませんが、またそれが小学校になった時、中学校になった時に同じ教育をすると蘇っていくかもしれないからです。
大切なのは繰り返しの教育だと思います。
私たちの医学部の教育も卒前、卒後、専門教育と、繰り返し行っていますので、やはり継続的に行わないと意味がないはずです。
紙芝居や絵本などから始めても良いのではないでしょうか。
 ~Question4~
~Question4~
鈴木)
先生は日本ペインクリニック学会の「神経障害性疼痛薬物療法ガイドライン改訂第2版」をまとめられましたが、神経障害性疼痛治療における医療用麻薬の役割をがん性と非がん性でお教えいただければと思います。
山口)
このガイドラインの目的は痛みの診療に携わる全ての医療者への啓発、教育です。
神経障害性疼痛と言う概念を広く知ってもらい、理解してもらい、適切な薬物療法を普及させるためのものです。
以前は、痛みの治療薬と言えばNSAIDsといった考え方を、痛みの病態に合わせた薬の選択を、例えば、神経の障害による痛みに対する薬の使い方について多くの医療者に理解してもらうことを目的に作成されていますので、がんの痛みに特化して作られたものではありません。
ですので、このガイドラインをそのまま記載された内容どおりにがん性の神経障害性疼痛に当てはめるのは無理があります。
例えば、薬の選択順です。
非がん性の神経障害性疼痛であれば、第一選択はプレガバリンやデュロキセチンといった鎮痛補助薬と呼ばれている薬で、第三選択に位置づけされている医療用麻薬の選択は慎重でなければなりません。気を付けていただきたいのですが、第一選択や第二選択の薬が奏効しないという理由だけで、第三選択薬である医療用麻薬を安易に選択してはならないということです。医療用麻薬が第三選択薬に位置しているのは、極力その使用を避けなければならないと、解釈すべきでしょう。
一方、がん性の神経障害性疼痛であれば、考え方は非がん性と全く異なります。まずは、WHO方式がん疼痛治療法にしたがって強い痛みであれば医療用麻薬が第一選択薬であるべきです。医療用麻薬の処方が躊躇されてはなりません。そして、医療用麻薬に抵抗する痛みである場合に鎮痛補助薬が併用されるべきです。
また、注意してほしいことは、鎮痛補助薬が神経障害性疼痛全てに有効であるというわけではありません。そして、鎮痛補助薬が医療用麻薬に比べて副作用が少ないとも言えません。鎮痛補助薬の多くは神経系に作用する(抑制)薬ですので、副作用に注意しなければなりません。
鈴木)
強いがん性疼痛の場合には積極的な「医療用麻薬」の処方という考え方になるわけですね?
「鎮痛補助薬」を使用する事によって医療用麻薬の量を減らすという事はどうなのですか?
山口)
医療用麻薬が一定量投与されていて、副作用が問題となっている際には、鎮痛補助薬を併用することで、医療用麻薬の投与量を減らすことができ、結果的に副作用が減り、痛みの管理が良好になることはよくあります。
しかしながら、がん性の痛みに際しては、まずは、痛みの緩和に必要な十分量の医療用麻薬を投与するということを怠ってはいけません。
~Question5~
鈴木)
一般社団法人医薬品適正使用・乱用防止推進会議を設立し、ほぼ1年経過しました。これまで、医療用麻薬や睡眠薬の適性使用と乱用防止をホームページで啓発活動を行い、教育用DVDやパンフレットの作成などの活動を行っております。最後に、先生から当法人へのメッセージをお願い致します。
山口)
ぜひ医療用麻薬に関して偏った考え方の社会にならないような国民・市民の意識付けをしていただく団体にして欲しいなと思っています。
今、アメリカでは「オピオイドクライシス」という問題を踏まえて、医療用麻薬の使用が極端に抑えられるようになり「医療用大麻の方が良いのではないか」と言った風潮がみられるようになっています。医療用大麻があれば医療用麻薬で亡くなる人が減るのではないか、と言うような議論が出ている位おかしな方向にシフトしていってしまっています。
ですから、医療用麻薬の適正使用、必要な患者に処方されことと乱用や不適切使用を防止することを両立させていくために何ができるか考えていく必要があります。
今、日本では医療用麻薬の消費量が他の先進国と比べて低迷していることを背景に、「規制緩和」という声が大きくなりつつあります。
確かに一部の規制緩和は必要であると僕自身も思っています。
日本人は道徳が保たれていますし、これまでの歴史的、社会構造、医療保険システムを考慮すると、医療用麻薬が不適切に流通することはないと思います。
「薬局と患者の間」の規制緩和ではなく、「薬局」であるとか「製薬会社から薬局」「問屋から薬局」であるとか薬局間の流通に対する規制緩和はいいかと思うんです。
ただ、一度医療機関から離れた医療用麻薬に対する規制に対しては、相当厳密にやっていく必要があります。
今でも不十分な所があると思うのは、亡くなった患者の元にある医療用麻薬をきちんと回収できていないところです。
このような不要になった医療用麻薬を回収できるようなシステムを作ることが重要です。
このようなシステムがなく、社会に医療用麻薬が氾濫してしまっているのが米国の社会です。
日本の良いところは伸ばしていく、悪いところは改善していくという事を推進していって欲しいと思います。
「知って欲しい思い」
最後に、「非がん性慢性疼痛に対するオピオイド鎮痛薬処方ガイドライン」を日本で初めて作成した際の私たちの思いを知って欲しいと思います。
医療用麻薬で患者を救うこと以前に、その弊害から患者を守り、さらには先人が維持してきた医療用麻薬の秩序を守り続けるという思いです。
医師の下で医療用麻薬が適切に管理されれば、ひいて言えば「必要な患者」に「必要最小限の量」を「必要最小期間」投与するという考え方が定着する事なのかなと思います。そして、一番大切なことは医療用麻薬は「やめられる薬」だという事を多くの人に知ってもらいたいと考えています。医療用麻薬が、医療に必須の薬であり「必要な時に使う薬」というイメージになっていただければと思います。
そういった考え方をまずは医療者、そして次に市民に啓発出来ればと思います。
是非、この団体にそういった啓発活動を幅広く、継続して行っていただければと思いますし、日本における素晴らしい医療用麻薬の規制方式・管理方式を維持していくために活躍していただきたいと思います。

後記
山口先生はとても活動的で、当日も栃木県の壬生町から東京まで出て来てくださいました。
先生は基礎研究にも理解が深く、また薬剤師への理解もとても深く、一緒に汗を流して頑張ろうと言う気迫を強く感じました。また、オピオイド問題でも日本の良きシステムを守り、オピオイド問題を海外から日本に持ち込ませないと言う信念を感じました。今後もオピオイドの適正使用と乱用防止に深く関わられ、多くの仲間と共により良い路を示して、導いて行かれると確信しました。
鈴木勉(すずきつとむ)プロフィール
◆1979年星薬科大学大学院博士課程修了、同大学助手、講師、助教授を経て、1999年教授、2015 年特任教授・名誉教授
◆1984-86年ミネソタ大学医学部および米国国立薬物乱用研究所研究員
◆2002年WHO薬物依存専門委員会委員、2013年厚労省薬事・食品衛生審議会指定薬物部会長、2015年麻薬・覚せい剤乱用防止センター理事等
◆日本薬理学会理事、日本アルコール薬物医学会理事長、日本緩和医療薬学会理事長等歴任
現職:星薬科大学特任教授・名誉教授
